| ◇ 陶磁器 |
イメージイラスト模写 (拡大可能) |
| 陶磁器の起源は数千年前のエジプト、メソポタミア、中国 |
 |
| 日本の縄文時代に遡るとされています。当時、粘土でタイル、 |
| レンガも作られています。 |
|
| ♢日本での発展 |
| ◈縄文時代の陶芸 約8000年前から作られた縄文土器は |
| 焼成温度600度前後で造られた世界で最も古い土器の一つ |
| です。 |
縄文土器「深鉢」 BC8000年~ |
|
|
| ◈弥生時代の陶芸 BC2世紀からBC3世紀に作られ、全 |
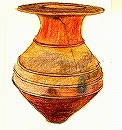 |
| 国に広がった弥生土器は約800度で焼成され、水器、鍋、 |
| 鉢が作られた。 |
|
| ◈須恵器(すえき) 大陸から入ってきた技術によって作 |
| られた須恵器はろくろで成形して、穴窯の高い温度で焼成 |
| されました。焼成中に灰がかかり、緑色になるものもありま |
| す。須恵器は鎌倉時代まで造られました。 |
弥生式土器 BC200年~ |
|
|
| ◈奈良時代の陶芸 中国唐、元の時代に造られた唐三彩 |
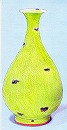  |
| の影響を受けて造られた奈良三菜は釉薬を使った日本最 |
| 古の陶器です。壷、塔,盤、碗が正倉院に保存されてます。 |
| |
| ◈鎌倉時代の陶芸 陶器の製造は瀬戸地方が中心とな |
| り、ろくろを使い、高温で灰釉や鉄釉を使い、また線彫り、 |
| 型押し、張付けなどの模様のある陶器が造られた。 |
中国・元「彩色壺」 中国・韻「彩陶壺」BC2500-BC2000 |
| |
|
| ◈室町時代の陶器 日本六古窯と言われる瀬戸、常鍋、 |
|
| 信楽、越前、丹波、備前に加え、各地で陶器が製造されま |
 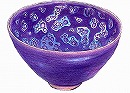 |
| した。また中国から輸入された栄磁の影響も現れてます。 |
| |
| ◈安土・桃山時代の陶芸 京都で楽焼が興り、瀬戸や美 |
| 濃地方で茶器、水指、香合などが陶磁器が多く製造されま |
| した。桃山後期には朝鮮半島の影響も加わり、高取焼、上 |
| 野焼、薩摩焼、唐津焼、萩焼が盛んに造られました。 |
信楽焼 中国・南宋「曜変目茶碗」 |
| |
 |
| ◈江戸時代の陶芸 |
| 江戸時代始、1610年には有田の泉山で陶石が見つかる |
| と、伊万里焼と呼ばれる磁器の製造が盛んになりました。 |
| 1647年有田の酒井田柿右衛門が錦磁器を造り、1690年 |
| 代まで、赤、緑、黄色で彩色された多彩色の磁器「柿右衛 |
| 門様式」が流行しました。図柄も余白を活かした絵画的な |
| ものが特長です。 |
唐津焼 |
| 柿右衛門様式の色絵磁器は伊万里港からヨーロッパへ |
|
| 輸出されるようになり、アールズーボー様式の磁器の図柄 |
 |
| に影響を与えました。ドイツのマイセン窯、フランスのシャン |
| ティ窯にその徴候が見られます。 |
| 後に有田の磁器の技術は京都、九谷、磯部へと伝承され |
| ました。 |
|
| ◈窯の歴史 |
有田焼 柿右衛門様式 |
| ◊縄文土器、弥生土器・・・AD5世紀古墳時代まで・・野焼 |
|
| ◊須恵器からの陶磁器・・飛鳥~江戸時代末まで・・穴窯 |
|
 Google Translation
page ←Multilingual translation
Google Translation
page ←Multilingual translation