| ◇ガラス工芸 |
イメージイラスト模写 (拡大可能) |
| ◇ガラスの技法 |
|
| ♢コア技法 |
|
| 芯を耐火粘土などで型取り、全体に色ガラスをつけ、 |
|
| 冷却後に中のねんどを掻き出すもの。 |
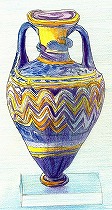 |
| ♢モザイク技法 |
| 型を使う製法、外型にモザイクのガラス片を敷き詰め、 |
| 上から内型を載せ、更に重しを載せ窯で焼成するもの。 |
| ♢鋳造技法 |
| 開放式の鋳型が主流であった様です。 |
| ♢熱垂下法 |
| 例えば、円筒をした耐火物の上に板ガラスをのせ、下か |
| ら熱を加えることによって、板ガラスの中側が下に垂れ |
| 下がる方法などで製品をつくるもの。 |
| ♢吹き技法 |
エジプト コアグラス BC1500-BC1300 |
| 溶けたガラスを吹き竿の先につけ、息を吹きながら |
|
| 膨らました後、吹き竿からガラスを切り離し、口の部分 |
|
| を加熱しながら整えるもの。 |
|
|
|
| ◇絵付け |
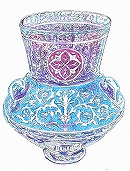 |
| ♢エナメル絵付け |
| 色ガラスの粉を顔料として絵を描き、600度程で焼成し |
| てつくる絵付け方。200年頃ローマで発明、イスラム世 |
| 界で発展、以後普及する。 |
|
|
|
| ◇ガラス工芸の歴史 |
| ♢古代 |
| ◈BC3000年からBC2000年頃のエジプトやエーゲ海 |
| のクレタ島で作られたコアグラスやガラスの球やガラス |
イスラムグラス モザイク技法 800年ー1500年 |
| 棒の装飾品が発見されてます。 |
|
| ◈BC1500年からBC26年、エジプト、メソポタミア、シリ |
|
| アで押し型コア技術でガラス製品が作られるようになり、 |
|
| 普及しました。 |
|
|
|
|
|
| ♢ローマ時代 |
 |
| ◈ローマグラス |
| ローマ時代にはコア技法、押し型法に加え吹き技法が |
| 完成して、さまざまな形のガラス製品が作られるように |
| なりました。その技術はローマ帝国滅亡後、北ヨーロッ |
| パに普及しました。 |
| ◈12世紀、ビザンチンでモザイク画の発展からステンド |
| グラスが産まれ、ステンドグラスといっしょにガラス技術 |
| がイスラム世界へ普及しました。ペルシャ時期のガラス |
| 製品は日本にも渡って来ました。 |
正倉院蔵 ササン朝ペルシャ時代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♢近世 |
 |
| ◈ルネッサンスの時代、ウ"ェネツィアでガラス工芸は普 |
| 及しました。 |
| ◈ウ゛ェネチアグラス |
| ガラス工芸品はエナメル絵付が好まれ、加えてクリスタ |
| ッロの発明で透明性の高い無色ガラスが普及しました。 |
| 繊細で優美なウ゛ェネツィアグラスは高級工芸品として |
| ヨーロッパの宮廷や富裕層に好まれまれ、全ヨーロッパ |
| に普及しました。 |
| その後、ボヘミアグラスなどヨーロッパ各地でガラス工芸 |
| が起こりました。 |
ボヘミアグラス(1725年ー1730年頃) |
|
|
|
 |
| ♢アール・ヌーボー |
| フランス(1890年~1910年)で興った動植物をデザイン |
| 化したデザイン、アール・ヌーボーの流れはガラス工芸 |
| にも取り入れられ、斬新なガラス工芸品を産み出しまし |
| た。代表的作家としてエミール・ガレ、ドーム兄弟、ティ |
| ファニーなどが上げられます。 |
|
|
|
|
アール・ヌーボー 19世紀 |
| ♢アール・デコ |
|
| 20世紀に入るとフォービズム、キュービズム、シュール |
 |
| リアリズムと新しい美術の流れが興り、ガラス工芸もそ |
| の流れの中で、図柄がフォービック、キュウビック、シュ |
| ールな図柄に変化しました。またガラス素材の追求が |
| なされ、ガラス製品も大量に生産されて、ガラス工芸は |
| 幅広い広がりを見せました。 |
| アール・デコの代表作家としてルネ・ラリックス、モーリス |
| ・マリノなどが上げられます。 |
|
|
アール・デコ「昆虫文」20世紀 |
| ♢現代 |
|
| 1960年以降、作家個人で溶解炉を設置して創作する様 |
|
| になり、さまざまな個性的なガラス工芸品が産み出され |
|
| ています。 |
|
