| 日本画と油絵の違い |
| ◇日本画と油絵 |
| ♢ 明治初期、ヨーロッパから入ってきた絵画を油絵(油彩画)と呼んだ。それに対して、今まで絹 |
| 本や麻紙に描いていた「大和絵」、「障壁画」、「水墨画」などをまとめて日本画と呼ぶ様になった。 |
  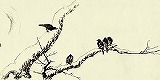 |
| 日本画(大和絵・障壁画・水墨画/模写) |
|
| ♢ 日本画 |
| 日本画の絵具、岩絵具は鉱石を砕いて、砂状の粒子から小麦粉状の粒子に分けた岩顔料である。従って、一色で |
| 10から12の色が作られる。微妙に変化した色が作られる岩絵具の特徴として、絵のなかにグラデーション的表現を |
| 表す時に適している。その特徴を活かして絵が出来上がれば、画面はより統一感のある安定したものとなる。 |
| また、絵具の中では天然の色(人間が作れない色の明るさ、軽さ、深みのある色)が豊富であり、発色が美しいと言 |
| える。 |
|
| 使い方は岩絵具を絵皿に取り、顔料の2/3程度の膠液を入れ、指で膠と粒子を絡ませて溶き、そこに水を加えて使 |
| 用する。砂粒状の粒子の絵具を使う時は筆で塗るというよりか、筆で絵具をすくって画面に載せるといった具合となる。 |
|
|
|
|
  |
| 油絵(ヨーロッパから来た絵画・模写) |
| ♢ 油絵 |
| 油絵の絵具、油絵具は植物性の乾性油でペースト状に練り合せた絵具である。絵具の状態として、透明、不透明、 |
| 半透明の絵具があり、更に溶き油の種類によって、光沢、艶消し効果を画面に表現することが可能である。 |
| また、厚塗り、薄塗り、重ね塗りが可能である。最も多様性に富んだ絵具と言えるのではないだろうか。 |
|
| 使い方はキャンバスに色で地塗りし、次に描くものの元となる色で下塗りし、順次絵具を塗り重ねていく。 |
|
|
|